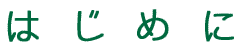
|
|
|
|
産業保健人間工学会認定作業管理士《仮称》 ―産業保健人間工学の立場から考える作業管理の役割― 産業保健人間工学会は昨年創立10周年記念大会を終えて一つの区切りをつけた。 本年度は次世代産業保健人間工学に向けての出発の年である。 産業保健人間工学会の新たな活動の一つとして産業保健人間工学会認定作業管理士(仮称)制度発足に向けての検討が挙げられる。 この検討は本学会副会長の岸田考弥教授を委員長として模索してきた。 今年、実行組織として(財)日本予防医学協会の参画を得、本格的に実施に向けての準備が開始されるに至った。 そこで、第11回大会において第1回産業保健人間工学会認定作業管理士(仮称)ワーキング委員会が開催されることとなった。 委員会は産業組織心理学者、産業保健師、産業看護師、産業医、経営工学者、体育学者、農作業改善指導にかかる実務家、海上労働科学研究者そして人間工学者らによって構成されている。 したがって、作業管理士(仮称)の適用範囲も、産業医学、産業保健学、産業看護学、経営工学、農業、水産等々の他分野にまたがる。名称も作業管理士という一つのくくりが妥当であるのか、 それとも、作業管理士(産業医学)作業管理士(作業保健)、作業管理士(生産管理)、作業管理士(体育)、−−−等々とすべきか、はなはだ困難な課題を山積している。 しかし、このあたりから手をつけないと作業管理士資格認定への必要条件、十分条件が決まらなくなる。さらにそれが決まらないと、認定のための必修研修科目と選択研修科目の設定が決められない。 第1回委員会は最初から悩ましい仕事を背負うこととなるが次世代産業保健人間工学会のために粉骨砕身してことにあったって頂くことを願うばかりである。 そこで、本機会を利用して産業保健人間工学と作業管理についての私見(思い入れ)を述べさせていただく。 この一私的見解をたたき台として産業保健人間工学会認定作業管理士(仮称)のあり方討議に花を咲かせていただければ本望である。 会員諸兄がご存知のように人間工学は二つの英語名称を持っている。一つは20世紀初頭に米国で誕生した「Human Engineering」を源とする「Human Factors」である。 この用語を端的に日本語に置き換えると「人的要因」である。すなわち、この語の持つ意味から推測すると、Human Factors(人的要因)=人間工学とは、人間の特性を理解し、応用する学問と解釈できる。 一方、英国で生まれた「Ergonomics」という英語がある。Ergonomicsはギリシャ語のErgon (筋力、作業、仕事)とnomos(正常化、法則、習慣)との合成語である。 それゆえに、Ergonomicsをを仕事の適性管理と解釈することができる。 産業保健人間工学は基礎知識としてHuman Factors(人間の特性を理解し、応用する学問)を修得し、その知識を用いてErgonomics(仕事の適性管理)が本来持っている目的に沿って実践活動する学問といえる。 すなわち、産業保健人間工学は「働く場の人的・物理的条件整備」と「そこで働く人々の健康確保と安全/安心の確保」さらには「働く人々が身を寄せる組織体の健全経営のあり方」を主対象としている。 産業保健活動を行政用語で表現すると労働衛生活動である。労働衛生活動には三管理と呼ばれている三つの活動がある。すなわち、健康管理、作業環境管理そして作業管理である。 健康管理と作業環境管理の二つはその言葉の響きから何となく理解できる。しかし、作業管理の役割に関しては産業保健従事者においてすらわかりにくい。 むしろ、作業管理を英語で表現した方がわかりやすい。英語では「Work Conditions and Ergonomics」と表現されている。 それゆえに、狭義に解釈すれば、作業管理と産業保健人間工学を同意語として捉えても無理はない。 一方、日本において現在示されている作業管理の役割を調べる必要がある。そこで、作業管理の役割とその意義を理解するために作業管理が説明されている三つの資料を観察することする。 最初に、厚生労働省労働基準局編集の「労働衛生のしおり」を紐解いてみることとする。「労働衛生のしおり」の平成18年度版に記載されている労働衛生管理の基本― ハ.作業管理(p43)―には次のように記述されている(以下、原文抜粋)。 〜「有害な物質や有害なエネルギーが人に及ぼす影響は、作業の内容や個々人の健康の状態や作業のやり方によって異なります。 これらの要因を適切に管理して、作業環境の悪化を防止し、労働者への影響を少なくすることが作業管理です。 作業管理の進め方としては、作業に伴う有害要因の発生を防止・抑制したり、暴露を少なくするために作業の手順や方法を定めること、 作業方法の変更などにより作業の負荷や姿勢などによる身体への悪影響を減少させること、保護具を適正に用い、暴露を少なくすることなどがあります。」〜。 さらに、平成18年度全国労働衛生週間実施要綱(労働衛生のしおりp10-p15)において、日常の労働衛生活動の総点検項目を明示している。 その中の作業管理に関係する事項を抜粋すると下記の項目が挙げられている(以下原文)。 ウ 作業管理の推進 (ア)自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進 (イ)作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善 (ウ)作業管理のための各種作業指針の周知徹底 (エ)適切な呼吸用保護具等の着用状況の確認と保守管理体制の充実 (オ)休憩、休養設備の点検、整備・充実 コ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防の推進 セ VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業におけるろうどう衛生管理対策の推進 ツ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の促進 ヌ 労働時間等労働条件の改善等の促進 次に、産業医業務の視点から見てみることとする。何故ならば、産業医は一つの職責上の業務として作業管理を行わなければならないからである。 そこで、日本産業衛生学会専門医制度における作業管理関連研修項目を観察してみることとする。 日本産業衛生学会は専門医の資格を与えるために設けた体系的基礎研修ガイドラインにおいて、作業管理関連講座として労働生理(時間)と作業管理(20時間)を組み入れている。 労働生理に関する詳細な項目は次の通りである(以下原文)。 ○疲労の種類とメカニズム ○疲労調査法 ○産業疲労と作業能率、ミス、事故 ○時間(日、週、季節)による生体リズムと疲労 ○各種労働態様と疲労(労働強度、夜間勤務、OA作業、監視作業、連続繰り返し作業接客業務、運転業務) ○労働適性と適応 ○母性保護 ○中高年齢者と労働 同様にして、作業管理として習得すべき項目は下記の通りである(以下原文)。 ○有害業務(振動、重量物挙上、VDT、キーパンチ、運転、引き金付工具等) ○作業負荷の評価(強度、動き、速度、精度、複雑性、判断量、拘束性、一連続作業時間、姿勢、チームワーク) ○ストレスの評価 ○職務設計 ○管理基準、作業標準 ○職場巡視(方法、評価、記録) ○衛生保護具(マスク、眼鏡、耳栓、手袋、前掛、長靴、耐熱・耐寒服) ○産業災害の動向 ○事故の背景(性格、時間変動、心理的背景、安全設計) ○安全設備管理、安全作業 ○安全保護具(安全靴、ヘルメット、保護眼鏡、安全帯) さらに実務研修としての作業管理では、次の研修課題を掲げている(以下原文)。 1.就業条件、作業工程、作業内容の理解とその変化に関する情報が把握できる。 2.個別作業の職務内容の理解に基づき、その負荷を評価できる。 3.スタッフとしての立場で作業管理に参加する意味が理解できる。 4.個人保護具の目的を理解し、適切な保護具の選定、装着の指導・管理ができる。 5.作業改善のための設備、冶具等の原理を理解し、その効果を評価できる。 6.安全管理の原理と主要な方法を理解し、専門家に協力できる。 7.作業方法(作業標準書)、作業環境改善の具体的行動計画を立案できる。 8.問題の大きさの把握に基づき、改善計画の優先度の判断ができる。 最後に、日本医師会認定産業医制度における作業管理関連研修項目を抜粋・紹介することとする(以下、原文抜粋)。 基礎研修 前期研修 作業管理 1)労働生理 中高年労働者、女子労働者、心身障害労働者、労働適性、疲労、作業強度、労働時間、休憩、作業姿勢、夜勤、単調労働、VDT作業 2)生物学的モニタリング 3)作業管理の事例 作業負荷の改善、標準作業の設定、作業者の教育訓練 安全管理、保護具を含める 基礎研修 後期研修 作業管理 1)労働生理 生体リズム、夜勤、疲労、労働時間、休憩、作業姿勢、労働強度、重筋労働、労働適性、単調労働、マン・マシンシステム等 職務設計 2)作業管理の事例 作業負荷の改善、標準作業の設定、ストレス管理、作業者の教育訓練等 3)個人保護具(呼吸保護具、防振具、耳栓、手袋、安全靴等) 4)安全管理と災害防止 生涯研修 専門研修 作業管理 1)労働生理 生体リズム、夜勤、疲労、労働時間、休憩、作業姿勢、労働強度、重筋労働、労働適性、単調労働、マン・マシンシステム等 職務設計 2)作業管理の事例 作業負荷の改善、標準作業の設定、ストレス管理、作業者の教育訓練等 3)個人保護具(呼吸保護具、防振具、耳栓、手袋、安全靴等) 4)安全管理と災害防止 以上、ここで紹介した3種の実例から現在日本で行われている、あるいは日本国内で求められている作業管理の役割が理解できる。 翻って、産業保健人間工学の役割を述べると労働衛生領域と労働安全領域との二つに分けられる。 これら二つの領域についてそれぞれ思いつくままに課題を挙げてみると、前者の労働衛生領域では、作業に関連して起きる筋骨格系障害(腰痛、頸肩腕障害、肘痛等々)の防止、 メンタルストレス、メンタルワークロードの軽減、メンタルヘルスケアーシステムの設計、さらには産業疲労対策などが考えられる。 筋骨格系障害に関する具体的な産業保健人間工学の介入としては作業/職場改善、職務設計が挙げられる。 従来の産業保健関連領域のアプローチと大きく異なることは産業保健人間工学の最終着陸点が開発/設計に定められている点である。 したがって、作業方法の改善、支援機器の開発導入を含む「改善」は産業保健人間工学の代表的な活動である。また、筋骨格系障害を物理学的/他覚的に捉える道具を持っているのも特徴である。 たとえば、バイオメカニックスの応用が挙げられる。ストレス関連課題に対する産業保健人間工学は一般的に用いられている心理学、精神医学等の手法に加えて、 人間工学が独自に創り上げた組織設計管理の手法を導入している。これは刺激因子がストレッサーに変貌する以前の真因(潜在因子等)段階で対処(解決)するための有効な武器として使われ、 これらによって誘発される障害の発症を最小限に食い止めることができる。言い換えれば、ストレス反応(ストレイン)にのみ注目し、介入するのみではなく、 ストレスとなる要因(ストレッサー)対策に力点を置いている。たとえば、ストレッサーの許容限界値の設定、あるいは組織体のメンタルヘルスケアー(組織設計管理)が挙げられる。 総じて、産業保健人間工学を説明するキーワードは「負荷と負担」と言える。 WorkConditions(負荷)とErgonomics(そこからもたらされる負担の様相を明らかにし、その軽減策を講じる)と言われている作業管理(Work Conditions and Ergonomics)と同じ役割を共有しているとも言える。 そして、産業保健人間工学の役割を説明するためのキーフレーズは職務と職務能力とのミスマッチを防ぐことによって労働安全・労働衛生を確保し、組織体の健康経営のあり方に資することである。 最近の急速な技術革新の進展、作業形態の多様化等に対応するためには、従来の作業環境管理を中心とした働く場の環境と作業条件等の整備そして健康診断を主業務としてきた健康管理で推し進める 法規準拠型の産業保健活動では対応できなくなってきた。そこで対応の一つとして、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)などが導入されているが、学際的な基盤がなく、 個々の領域での専門性に欠けて運用もいま一つの感がする。反して、学際領域に根ざした労働安全・衛生活動に科学と実践で対応できる学問が産業保健人間工学といえる。 これからは労働安全衛生活動に従事する産業保健従事者、生産性の向上を追いかける工学系技術者及び現場の管理者、あるいは危険または有害な業務に就いている者等々をはじめとする実務部隊に対して、 産業保健人間工学(作業管理)教育が重要となるであろう。 産業保健人間工学会の会員を概観すると会員それぞれの学問領域には労働安全活動を支える心理学、労働衛生活動を支える産業医学、産業保健学、産業看護学、体育学、栄養学、産業活動を支える機械工学、 生産技術、生産管理、経営管理、経済学等々の出身者から構成されている。これらの学問領域出身者は研究者、教育者、実務家と多岐にわたっている。さらには第二次産業のみならず、 農林・水産業等の第一次産業、第三次産業の領域を網羅している。以上の実態から、産業保健人間工学会の活動範囲は労働安全、労働衛生の確保にとどまらず、 生産性の向上への戦術を提案することも可能としている。 環境、安全、健康、生産の4視点から「仕事の適性管理」を検討し、「ヘルシーカンパニーの構築に貢献する実践学問と言える。 ここが従来の労働安全衛生領域に位置する学会と大きく異なる点である。同様にして、産業保健に特化している産業保健人間工学会はその活動範囲を既存の人間工学と違えている。 一言で表現すれば、着陸点をより鮮明に集中化している。さらに、経営工学関連学会では不得手とする労働の人間化と生産性の向上との融合策を得意としている。 それ故に、産業保健人間工学会は新しい作業管理のあり方を提唱し、その推進役を世に送り出すことが出来ると確信する所以である。 そこで、本レターの結びの言葉として、産業保健人間工学会認定作業管理士(仮称)が介入できる内容を個人レベル、職場レベル、企業レベルに分けて試案してみることとする。 個人レベル:ワークアビリテイーの向上に貢献することは産業保健人間工学の一つの重要な役割である。さらに、ワークアビリテイーの根幹をなすのがヒューマンリソースといえる。 そして、ヒューマンリソースは健康が基盤となる。そこで、産業保健人間工学会認定作業管理士(仮称)が介入できる個人レベルの戦術として、「生活機能の低下の防止」の介入が挙げられる。 具体的には体力年齢の引き下げ、生活習慣病を防ぐ一手段としての食生活指導、-----等である。 職場レベル:人間の特性を考慮して、働く場の改善、仕事自体の改善等を図ることである。 具体的には作業改善及び職務設計、支援機器/道具の開発・導入が挙げられる。さらにはこの種の改善活動を推進する人々を作り出すための教育・研修プログラムの開発、------等も含まれる。 企業レベル:ワークアビリテイーの診断・評価とそれに基づく人事・労務管理(賃金・処遇制度への踏み込みも対象とする)、組織のメンタルヘルスケアーを目指した組織設計管理、 改善活動等のサクセスストリーの水平展開、労働生産性向上に向けて個々の作業者の職務能力と課すべき職務とのミスマッチ防止に掛かる調整機能、-----等々である。 以上の試案は思いつきで記した項目である。これらに関する妥当な回答は委員会が作成してくれるものと信じて、筆を置きたい。 (産業保健人間工学研究Vol.8, Supplement, 2006.11, p1-4より抜粋) 「産業保健」に関する学会といえば「日本産業衛生学会」があります。そして、「人間工学」に関する学会といえば「日本人間工学会」があります。 1.「産業保健人間工学会」とは?! 「産業保健人間工学会」は、今から9年前に研究会として発足しました。発足以来、当会には従来の日本産業衛生学会、日本人間工学会では見受けられなかった様々な領域の人々が参加されました。例えば研究職者は言うに及ばず、農業関係者、企業の生産技術関係者及び人事・労務関係者、工業技術指導者等の多彩な実務家の顔ぶれをみることができました。会を重ねる毎に、参加者全員によって、当研究会を上記のいずれかの既成学会に部会登録して活動するか否かについて議論されました。しかし参加者一同からの回答はいずれの学会にも所属しない、独立学会としての設立希望でした。 2.何故? 第一の理由は、産業保健人間工学会の設立を希望した人々のすべてが、既存の二つの学会を"Theory and practice"の研究学会と位置づけた点にあります。同時に、産業保健人間工学会の設立を希望する全員が"Practice and its theory"の研究を望んだのです。事実、今までの当会の発表を概観しますと、あらゆる労働現場を対象として、現在発生している実例課題を取り上げ、それに対する解決策等を論議し、その解決案の普遍性を思案していました。今日、数ある学会のなかで「実務」を対象とする実践研究をScience of Artとして採択し、検討しているものは多くありません。 第二の理由は、産業保健活動を構成する三つの主要活動の一つである作業管理に焦点を合わせた学会の設立をめざした点です。ちなみに、作業管理を国際語で表現するとWork Conditions and Ergonomicsとなります。産業保健活動における最重要課題の一つとして、作業管理活動が挙げられます。なぜならば作業管理活動は、労働の場において引き起こされる健康障害、労働災害の根源を追求する学問領域といえるからです。しかし、作業管理活動が産業保健活動において重要な役割を果たす存在であるにもかかわらず、作業管理に関する労働衛生法規は少ないのが現状です。このような状況が作業管理実務の進展を遅らせている一因となっています。そして、この貧困な作業管理対策によって、今苦しんでいる人々が存在しているのです。 3.だからこそ、今「産業保健人間工学会」なのです。 産業保健人間工学会は、このような作業管理諸課題をScience of Artとして捉え、研究者として、実務家として世の中に役立つ解決志向型の研究を押し進めることを目的としています。そして、願わくは世に公的に認められる作業管理の専門家−作業管理士−を育て上げ、その資格認定学会としての存在をも目指しています。 産業保健人間工学会、この学会の名称を耳にされ、「おや、そんな学会があったの?」と首をかしげる方も多いかと思われます。しかし、本学会は国際的には認知され、海外の人々から多くの関心が寄せられています。国際人間工学連合(IEA)が発行しているIEAニュースレター(November 1996)でも産業保健人間工学会に関する記事が紹介されています。そこで産業保健人間工学会に関する紹介記事を転載します。 INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION Ergonomics International News and Information - November 1996に掲載された記事より The Society for Occupational Safety, Health and Ergonomics (SOSHE) was founded in Japan in 1991. It is a small society with an extraordinary amount of energy. It has had annual meetings with more than 100 participants every year. The meetings have a limited number of speakers as the members dislike parallel discussions and short discussion time. About 40% of the participants return year after year and 60% are local participants for one year only. This format has allowed ergonomists to meet many people with no apparent connection with ergonomics. An example is groups concerned with agricultural technology. They wanted to teach farmers good working postures and the management of working hours as well as cross-breeding of fruit and vegetables and soil improvement. Other related groups are industrial hygienists, occupational nurses, and industrial managers. At our meetings, we invited researchers and people with practical experience in occupational health, safety and ergonomics to consider solution-oriented approaches to the issues that directly confronted us and to consider as a group what issues would arise in the near future. Everyone in attendance participated in the meetings together, in fact as well as in name. In 1996, the society held its first conference at Chiba Institute of Technology (near Tokyo). Keynote speakers were Dr. Konz (Kansas State University, USA) and Dr. Kogi (Institute for Science of Labor, Japan). There were 17 additional papers plus a symposium 'Ergonomic Activities in Occupational Health' with panelists from occupational nursing. occupational medicine, industrial health and safety management in corporations, and psychosociology. The presentations were related to applied ergonomics and involved the search for practical ways to resolve problems. Some of the talks discussed failures of projects, providing valuable lessons for all the participants. We are a small group that cannot publish a journal but are planning to publish a newsletter. We will have a question and answer column for members that will enable everyone to consider and solve occupational health, safety and ergonomic issues. In the near future, we would like to hold a meeting in English to allow participation of both Japanese and overseas colleagues. (産業保健人間工学研究Vol.1, Supplement, 1999.11, p1-3より抜粋) |